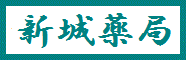次の記事に目が留まりました。


私は仕事をしながら介護を経験したことがあるため、以前に次の投稿をしています。
私の場合は薬局が1階で住まいは上の階だったため介護との両立ができたのだと思いますが、ほとんどの方は職場と被介護者のいる自宅とが離れているでしょうし、高齢者が増えると共に被介護者も増えますから、現在の就業状況では私は介護離職は増え続けるだろうと思っています。
介護離職について、次のページに下記がありました。

介護離職とは、家族や親族の介護をするために退職することを指します。厚生労働省が発表している「雇用動向調査」によると、2021年に離職した方は717万2,500人にのぼります。そのうち、「介護・看護」を理由に掲げた方の割合は1.3%、つまり約9万3,000人の方が介護離職を余儀なくされているのが現状です。
さらに細かく調査結果を見ていくと、男性・女性ともに40代以降の介護離職者数が増えており、45歳~49歳で辞めた方の割合は男性で1.5%、女性で4.7%にのぼりました(介護・看護による離職者数を100%としたときの割合)。
前出の記事には、企業側も対策を模索していることが書かれていました。
富士通(川崎市)は就業規則で介護休業を「介護・介護準備休職」と表記している。介護サービスを選ぶなど、仕事と両立できる体制を整えるために休む――という本来の趣旨を伝える狙いがある。社員が「介護に専念する期間」と誤解すれば、入浴やトイレなどの介助を直接担って疲弊し、復職が困難になる心配があるためだ。担当者は「仕事で能力を発揮してもらうため、両立支援は重要な経営課題だ」と語る。
また、厚労省が策定した指針について、次が書かれていました。
厚生労働省は今年7月、企業が両立支援に取り組みやすいよう、具体策を示したガイドライン(指針)を策定した。社員に「自分で介護をしすぎず、介護保険サービスを利用する」よう呼びかけることや、急に休んだ社員の業務をカバーする体制作りを求めた。
国と企業側が模索しながら少しずつ進んでいることが記事から読み取ることはできましたが、どれだけの離職を防ぐことができるのでしょうか。
私は、介護は社会全体で取り組まなければならない大きな課題だと思っているので、政府と企業側、そして自治体との連携に早急な対応を願うばかりです。