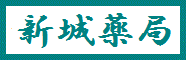以前、↓の投稿をしましたが、その後主人の不整脈は再発し、2年後の2023年に再手術を受けました。
再手術後も経過観察されているのですが、再手術から2年後の今年の7月にまた不整脈が現れたのです。
主治医は「緊急に手術が必要という状況ではない」と言って、月に一度の心電図検査とBNPの数値を診ているとのことでした。
BNPについて、私はあまり知識がなかったのでネット検索で次のページを読みました。
上ページに次が書かれていました。
BNP(Brain Natriuretic Peptide、脳性ナトリウム利尿ペプチド)は、心臓の主に心室から分泌されるホルモンの一つです。
心臓に過度な負荷がかかると、心筋細胞からBNPが血液中に放出され、体内の水分やナトリウムの排出を促すと同時に、血管を拡張し血圧を下げる効果を発揮します。これにより、心臓への負担を軽減する働きを担います。
BNPは心不全の診断や重症度の評価にとって非常に重要な指標です。

主人の場合もBNP値が上がると3度目の手術を受けなければならないのですが、夏になって不整脈が少し落ち着いたようで、秋に予定されていた3度目の手術は未定となりました。
BNPが上がらないことを願うばかりですが、そのBNPについてわかりやすく書かれた記事がありましたので紹介させていただきます。

心不全について、上ページには次が書かれていました。
心不全は、全身に十分な血液を送れなくなり、息切れやむくみなどの症状が出る病気の総称です。糖尿病や高血圧などの生活習慣病が危険因子となり、心肥大などの心疾患を発症することがあります。心疾患が進行して心不全につながります。心不全の患者は、国内で約130万人と推定されています。呼吸困難などの発作が起きる急性期と安定期を繰り返し、体の状態が悪化していきます。
そして、心不全とBNPとの関係については次のように説明されています。
心不全の前段階の心疾患を把握するのに、「BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)」という心臓から出るホルモンが手がかりになります。このホルモンは、血管を広げたり、体内の余分な水分の排出を促して血圧を下げたりする作用があります。心疾患があると、心臓が自らの負荷を減らそうと、生成するホルモンの量を増やします。このホルモンと同時に、「NT―proBNP」というたんぱく質も放出されます。
これらのホルモンやたんぱく質の血中濃度を測ることで、心疾患や心不全の可能性を判定できるようになりました。BNP検査と呼ばれるもので、今年3月に改訂された「心不全診療ガイドライン(指針)」でも心疾患や心不全の進行を測る指標に位置づけています。
上記事にもありますが、心不全は糖尿病や高血圧などの生活習慣病と深いかかわりがあるため、人間ドックなどの検診で生活習慣病を指摘された場合はBNP検査を受けるよう勧められるようです。
上記について、特にシニアの方々にはご記憶いただければと思います。